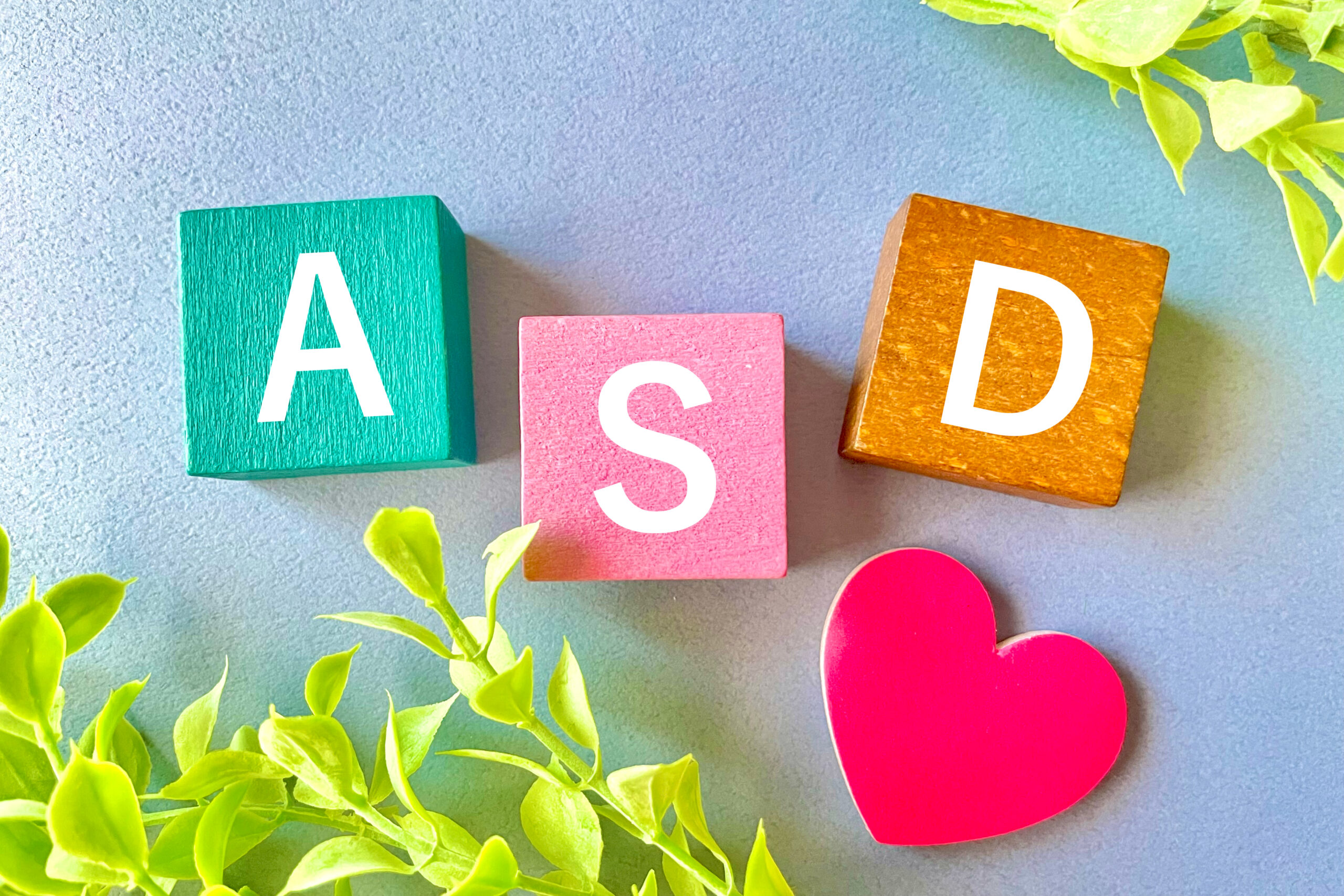「仕事のコミュニケーションがうまくいかない」
「自分のペースが周りと合わない」
そんなお悩みはありませんか?
ASD(自閉スペクトラム症)の特性は、人によってさまざまですが、自分の特性を理解し、適切な環境を整えることで、より働きやすくなります。
本記事では、ASDの特性と仕事への影響、そしてその活かし方について詳しく解説します。
ASDとは?主な特性を解説
ASD(自閉スペクトラム症)は、「Autism Spectrum Disorder」の略で、発達障害の一つです。
先天的な脳の働きの違いにより、他の人と比べて感じ方や考え方、行動の仕方に独自の傾向が見られます。
ASDは「スペクトラム(連続体)」という言葉の通り、人によって特性の強さや現れ方に幅があります。
一人ひとり違った特性を持っているため、「これがASDの人の特徴」と一括りにすることはできません。
ASDの診断は、主に以下の2つの観点から行われます。
社会的コミュニケーションの特性
ASDの方は、人との関わり方やコミュニケーションの面で特有の傾向が見られることがあります。
- 相手の気持ちや意図を読み取るのが難しい
- 暗黙のルールや場の空気を察するのが苦手
- 一方的に話し続けてしまうことがある
- 表情や声のトーンから感情を察するのが苦手
こうした傾向は「冷たい」「変わっている」と誤解されやすいことがあります。
しかし、見方を変えると「正直で誠実」「一貫した対応ができる」といった強みにもつながります。
行動や興味のパターンの特性
- こだわりが強く、決まったルーチンを崩されると不安を感じる
- 特定の分野や物事に強い興味を持ち、深く探求する
- 音や光、においなどに敏感(または鈍感)
- 予想外の変化に強いストレスを感じやすい
こうした特性は、日常生活や職場での困りごとにつながることがありますが、反対に「高い集中力」「ミスが少ない」「専門性の高さ」などの形で活かされることもあります。
ASDの特性が仕事に与える影響とは?
ASDの特性は、日常生活だけでなく、仕事の中でもさまざまなかたちで現れます。
「仕事にうまくなじめない」「職場にいると疲れてしまう」
そんな悩みを抱えることがある一方で、ASDならではの強みが仕事に活かされる場面もあります。
ここでは、特性が活きる面と、つまずきやすい場面の両方を整理してみましょう。
職場で活きる特性
ASDの方が持つ特性は、一定の環境では強みになることがあります。
たとえば、「これ」と決めたことに集中できるタイプの人は、同じ作業を丁寧に続けることが得意です。
細かい違いにも気づきやすく、正確さや安定性が求められる業務では力を発揮できます。
以下のような特性が仕事の強みになりやすいとされています。
- 一つの作業に集中できる
- ルールや手順をしっかり守ることができる
- 物事に一貫性を持って取り組める
- 興味がある分野に対して深く掘り下げられる
- 感情に流されず、冷静に対処できる
「好きなことはとことん突き詰める」
そんな自分の性格を「こだわりすぎ」と言われたことがあるかもしれませんが、職種や環境が合えば、それはむしろ武器になります。
困りごとにつながりやすい特性
一方で、ASDの方にとっては「わかりにくい」「対応しにくい」と感じる仕事の場面も少なくありません。
たとえば、上司から「うまくやっておいてね」と言われて戸惑った経験はないでしょうか?
具体的にどうすればいいのかわからないまま進めてしまい、あとから注意された…というケースもあるかもしれません。
次のような特性は、仕事の中でつまずきの原因になることがあります。
- 抽象的・曖昧な指示に困る
- 急な変更やイレギュラー対応が苦手
- 雑談や人間関係に疲れてしまう
- 職場の音やにおいが気になって集中できない
- 同時進行の仕事やマルチタスクに混乱しやすい
こうしたことは、「努力が足りない」のではなく、感じ方や処理の仕方が人と違うだけのことです。
同じ職場でも「平気な人」と「つらい人」がいるのは、そのためです。
まずは「なぜうまくいかないのか」に気づくことが第一歩です。
そのうえで、自分の特性に合ったやり方を見つけていくことで、少しずつ働きやすさを広げていけます。
ASDの特性を「強み」として仕事で活かすには?
ASDの特性は、仕事において課題となることもあれば、大きな強みとなることもあります。
「こだわりが強い」「変化が苦手」といった面も、裏を返せば「正確」「安定」「誠実」といった価値あるスキルと捉えることができます。
自分の特性を理解し、適切な環境や工夫を取り入れることで、より快適に働きながら能力を発揮することが可能です。
ここでは、ASDの特性を仕事で活かすためのポイントを紹介します。
「集中力」を武器にする
ASDの方の中には、一つの作業に長時間集中できるタイプの人がいます。
これは、マルチタスクが得意な人には難しいことであり、仕事においては大きな強みになります。
- データ入力や集計業務
- プログラミングやコーディング
- 品質管理や検品などの細かいチェック作業
単調に見える作業でも、集中力を維持してコツコツ取り組める力は、組織にとって非常に貴重です。
「正確さ」や「こだわり」を品質に変える
細部へのこだわりが強く、「なんとなく」で済ませるのが苦手という人もいます。
これは仕事において、「ミスが少ない」「一貫性がある」「丁寧な仕上がり」といった評価につながります。
- 経理・会計など、数字に正確さが求められる仕事
- デザインやDTPなど、細かいレイアウトや配色にこだわる仕事
- マニュアルや手順書の整備・チェック作業
「完璧主義すぎる」と言われる場面もあるかもしれませんが、それは「品質にこだわる姿勢」として活かせます。
「一貫性」や「感情に流されにくさ」が信頼につながる
ASDの方は、感情よりも論理やルールを重視する傾向があるため、状況に関係なく安定した対応ができます。
- 情の波に左右されにくい
- 同じことを同じようにできる
- ルールを正しく守る
こうした特性は、安定感や信頼性として評価されやすく、マネジメントや品質保証といった分野でも活かされることがあります。
「専門性の追求力」を価値にする
興味のある分野に強くこだわり、知識や技術を深掘りしていく力も、ASDの方に多く見られる特徴です。
この探究心は、専門職や研究職、クリエイティブな分野などで大きな価値を発揮します。
- プログラミング言語を独学で極める
- 動物や植物などの知識が図鑑並みに詳しい
- ツールやソフトの使い方を深く理解している
こうした「深さ」は、まさにASDの方ならではの強みです。
ASDの特性と相性が悪くなりやすい仕事の傾向
ASDの特性は、良い・悪いというより、「どんな環境で活きるか」「どんな条件が負担になるか」によって評価が大きく変わります。
たとえば、「この仕事がうまくいかない」「人間関係がうまく築けない」と感じたとしても、それは努力不足ではなく、その環境が自分の特性と合っていなかっただけということも少なくありません。
無理に苦手な状況に自分を合わせようとすると、心身に大きな負担がかかります。
ここでは、ASDの方がストレスを感じやすくなる代表的な仕事や環境の傾向を紹介します。
高度な対人スキルが必要な仕事
人と接する場面が多く、柔軟なコミュニケーションが求められる仕事では、ASDの特性ゆえにストレスを感じやすくなることがあります。
- 接客業(飲食店・販売など)
- 営業職やカスタマーサポート
- チームワークや雑談の多い職場
こうした職場では、「言葉にされない期待」や「微妙な距離感」の調整が求められやすく、それが積み重なると、知らず知らずのうちに心がすり減ってしまいます。
自分のペースやスタイルを保つのが難しい環境では、気づかぬうちに「無理をしすぎている」こともあります。
臨機応変な対応を常に求められる仕事
日々の業務が予測できず、判断を自分で下さなければならない仕事では、ASDの方にとって「見通しの立たなさ」が大きなストレスになることがあります。
- イベント運営や受付など、来客対応が多く変化が激しい業務
- 医療や介護など、緊急性の高い場面が日常的にある業務
- 毎日の業務内容が大きく変わり、自己判断を求められる職場
スケジュール通りに物事を進めたい人にとって、次々と予定が崩れていく状況は、混乱や不安を引き起こしやすくなります。
「その場でうまく対応するよりも、じっくり準備してから臨みたい」
そんなタイプの人にとっては、方向性のまったく違う仕事スタイルかもしれません。
刺激の多い環境や感覚過敏に負担がかかる仕事
音・光・におい・人の動き。こうした環境的な刺激が、気づかないうちに集中力や体力を奪っていることもあります。
以下のような職場は、感覚的に疲れやすくなる傾向があります。
- 騒音の多い現場作業や工場
- 飲食・医療現場など、人の出入りや会話が多い環境
- オープンスペース型のオフィス
「仕事自体はできるのに、なぜか家に帰るとぐったりする」
そんなときは、業務内容ではなく職場環境そのものが原因になっている可能性もあります。
快適さは、人によってまったく異なるもの。自分に合った「居場所の条件」を知ることも、働きやすさへの第一歩です。
もちろん、ここで紹介したような仕事でも、環境の工夫や周囲の理解によって働きやすくなることもあります。
大事なのは、「この仕事が向いていない」と思ったときに、自分を否定するのではなく、「じゃあ、どういう働き方が合うんだろう?」と視点を少しずらしてみることです。
向き・不向きを知ることは、可能性を狭めるのではなく、選択肢を増やすことにつながります。
仕事で困りごとを感じたときの対策
ASDの特性がある方にとって、仕事の中で「なぜかうまくいかない」「人と同じようにできない」と感じることは少なくありません。
でも、それは能力の問題ではなく、「やり方」や「環境」が合っていないだけかもしれません。
ここでは、職場で起きやすい困りごとと、それに対してできる工夫をいくつか紹介します。
業務の進め方に関する対策
一日の仕事量が多く、何から手をつければいいか迷うときは、頭の中だけで整理しようとせず、紙やメモアプリなどに書き出してみると、気持ちが整理しやすくなります。
優先順位がつけづらいと感じたら、上司や同僚に「どれから着手すればよいか」確認するのも一つの方法です。
突発的な変化への対応策
「予定外の指示が飛んでくる」「急に仕事の内容が変わる」など、見通しが立たない状況では、気持ちが乱れやすくなることがあります。
そんなときは、反射的に対応せず、「一度確認してから対応します」とワンクッション置くと、頭を整理する余裕が持てます。
職場でのコミュニケーションの工夫
職場でのコミュニケーションは、あいまいな表現や「察する力」が前提になっていることも少なくありません。
「この作業、ざっくりでいいからやっておいて」
こうした指示に戸惑ったら、「どのくらいの精度が必要か」「いつまでに提出か」を具体的に聞いて確認することで、やるべきことが明確になります。
感覚過敏や疲れやすさへの対策
照明、音、におい、人の動き……そういった環境要因が少しずつ負担になっている場合、自分でも気づかないうちに疲労がたまっていることがあります。
「理由はよくわからないけれど、帰るころにはぐったりしている」
そんなときは、感覚的なストレスがかかっている可能性も視野に入れてみてください。
ノイズキャンセリングイヤホンを使う、座る位置を調整する、短い休憩を挟むなど、物理的な工夫が役立つこともあります。
困りごとをそのままにしてしまうと、知らず知らずのうちに心や体のエネルギーを削ってしまいます。
「どうすれば少しでも楽になるか」を考えることは、自分を守るための前向きな選択です。
ASDの特性を理解して、自分に合った働き方を見つけよう
ASD(自閉スペクトラム症)の特性は、一人ひとり異なります。
仕事をするうえで苦手に感じることもあれば、逆に強みとして活かせることもあります。
ASDの特性を理解し、自分に合った働き方を見つけることは、安定した就労につながります。
得意なことを活かし、苦手なことには工夫を取り入れながら、自分に合った仕事のスタイルを探していきましょう。
また、困ったときには一人で抱え込まず、支援機関や職場の理解者に相談することが大切です。
自分に合った環境を整えながら、無理なく働き続ける方法を見つけていきましょう。
あいち就労支援センターではASDにお悩みの方の支援も行なっています。
お悩みの方はぜひ当センターへご相談ください。