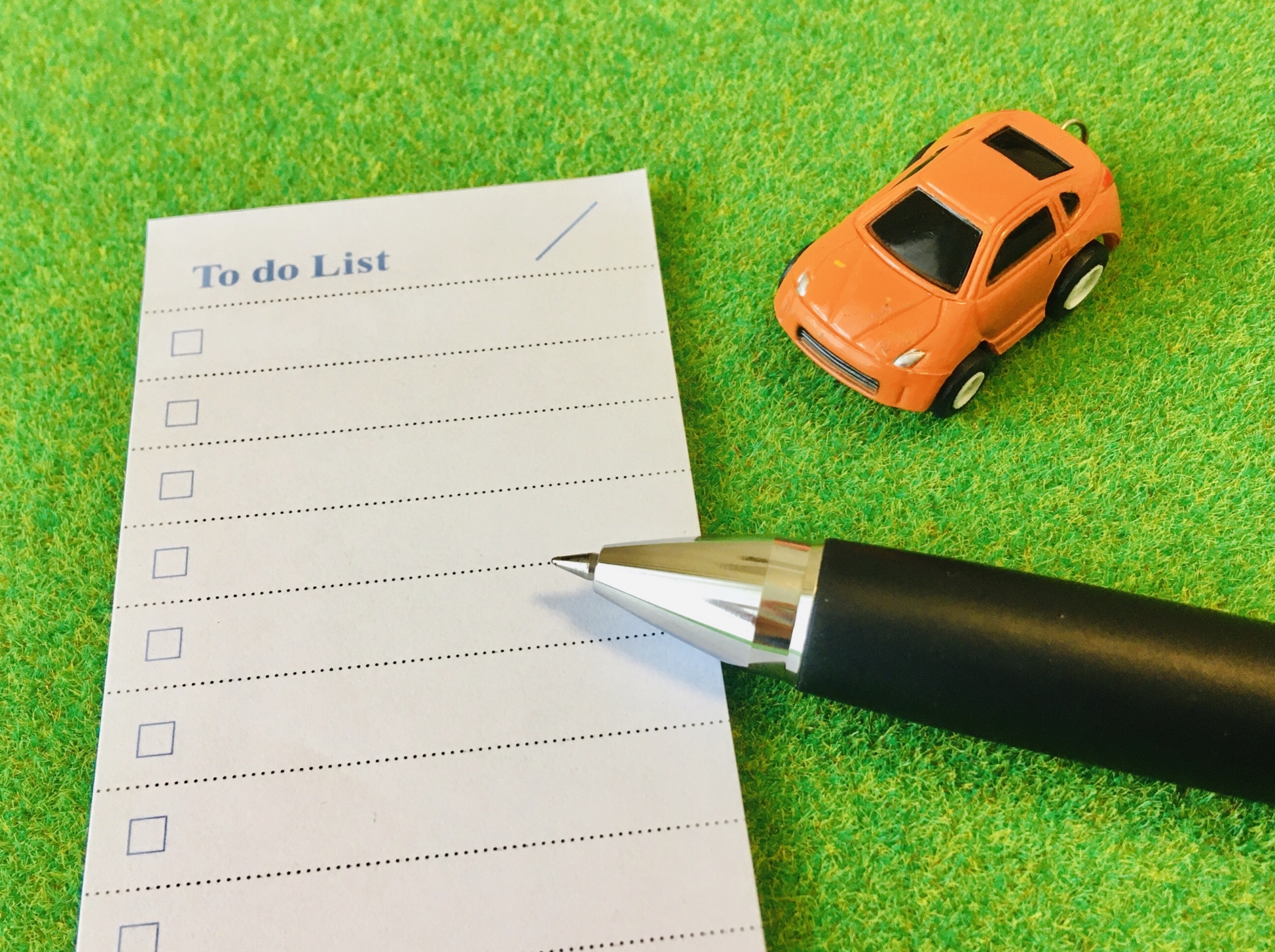― 自閉スペクトラム症の傾向がある人に向けて
「やらなければいけない」と頭では理解していても、体が動かず、作業に取りかかれないことはありませんか?
このような状態が続くと、自分に対して「やる気がないのではないか」「甘えているのではないか」と感じてしまう人も少なくありません。しかし、こうした反応には背景があることが多く、とくに自閉スペクトラム症(ASD)の傾向がある人にとっては、単なる気持ちの問題では説明できない事情が関係していることがあります。
行動を始められない
ASDの傾向がある人は、「行動を始めるまでの手順」を頭の中でイメージしたり、「次に何をすべきか」を予測したりすることに時間がかかることがあります。これは、課題を抽象的に捉えるよりも、明確な順序やルールがあるほうが理解しやすいという特性と関係しています。
たとえば、「レポートを書く」という課題に対して、どこから手をつければよいのか分からなかったり、始める前の準備に不安を感じたりすることがあります。また、作業中に予期せぬ変化があると、それに対応するために一度止まってしまい、その後再開するのが難しくなるケースも見られます。
こうした行動の「始めにくさ」は、本人の意思や意欲とは別のところで起こるものであり、努力不足や性格の問題として扱うことは適切ではありません。
「やる気が出ない」ときのチェックポイント
「なぜ動けないのか」が自分でも分からないときは、次のような観点から状況を整理してみると、現実的な手がかりが得られることがあります。
- 作業内容が十分に具体化されているか
- 行動を始めるための準備や手順が明確になっているか
- 集中できる環境や道具が整っているか
- 体調や疲労の蓄積が影響していないか
- 次に何をするかが見えている状態か
これらの点を一つひとつ見直すことで、個人の性格や能力に責任を求めるのではなく、課題に対応するための条件を整えることを優先することができます。
実行のための工夫
行動に移すことが難しい場合は、無理にやる気を出そうとするよりも、行動しやすい工夫を日常の中に組み込んでいくことが大切です。
まず、作業を「小さなステップ」に分けて考える方法があります。たとえば、「机に座る」「パソコンを開く」「文書ファイルを出す」といった行動を一連の流れとしてではなく、それぞれ独立した作業ととらえることで、行動を始める負担が軽減されます。
次に、行動のスイッチとなる「開始のきっかけ」を明確にしておくことも有効です。朝、決まった飲み物を用意する、作業用の音楽を流す、スケジュール帳を開くといった行為が「これから始める」という合図になり、頭の切り替えがスムーズになることがあります。
また、ToDoリストやタイマーなど、時間ややることを視覚化できるツールを使うことで、進行状況を確認しながら作業を進めやすくなります。とくにASDの傾向がある人にとっては、目に見える形で情報が整理されていることが、安心感につながります。
それでも難しさが続く場合は、周囲の人と状況を共有し、どの部分が負担になっているかを一緒に見直すことも大切です。ひとりで対処しようとせず、必要に応じて環境や手順を調整してもらうことで、行動を起こしやすくなる可能性があります。
「やる気」という言葉への向き合い方
「やる気がない」という言葉には、本人の努力や責任を問うような響きがありますが、実際には「やる気」というものが先にあって行動が生まれるとは限りません。むしろ、行動を始めてみて、少しずつ手応えを得ながら気持ちがついてくるという順序のほうが、現実には多く見られます。
ASDの傾向がある人にとって、「何をするか」「どう始めるか」「どこまでやればよいか」が分かりづらい状況では、行動に向かうきっかけ自体がつかみにくくなります。そのため、意欲の問題として処理するのではなく、「やりやすくする工夫」や「負担を減らす手順」が重要になります。
まとめ
やる気が出ないと感じるとき、その背景にはさまざまな要因が関係しています。特に、自閉スペクトラム症の傾向がある人にとっては、行動のきっかけが見つけづらかったり、予定外のことに対応するのが難しかったりすることが、行動全体の流れを止めてしまうことがあります。
自分の努力や性格の問題として受け止めてしまうと、解決の糸口が見えなくなることがあります。そうではなく、「何がやりづらくなっているのか」を冷静に見直し、「どうすれば少しでも動きやすくなるか」を試しながら、無理のないペースで調整していくことが、現実的な対応として有効です。
ちょっとした工夫を取り入れてみて、皆さんの生活がより良いものになることを願っています。