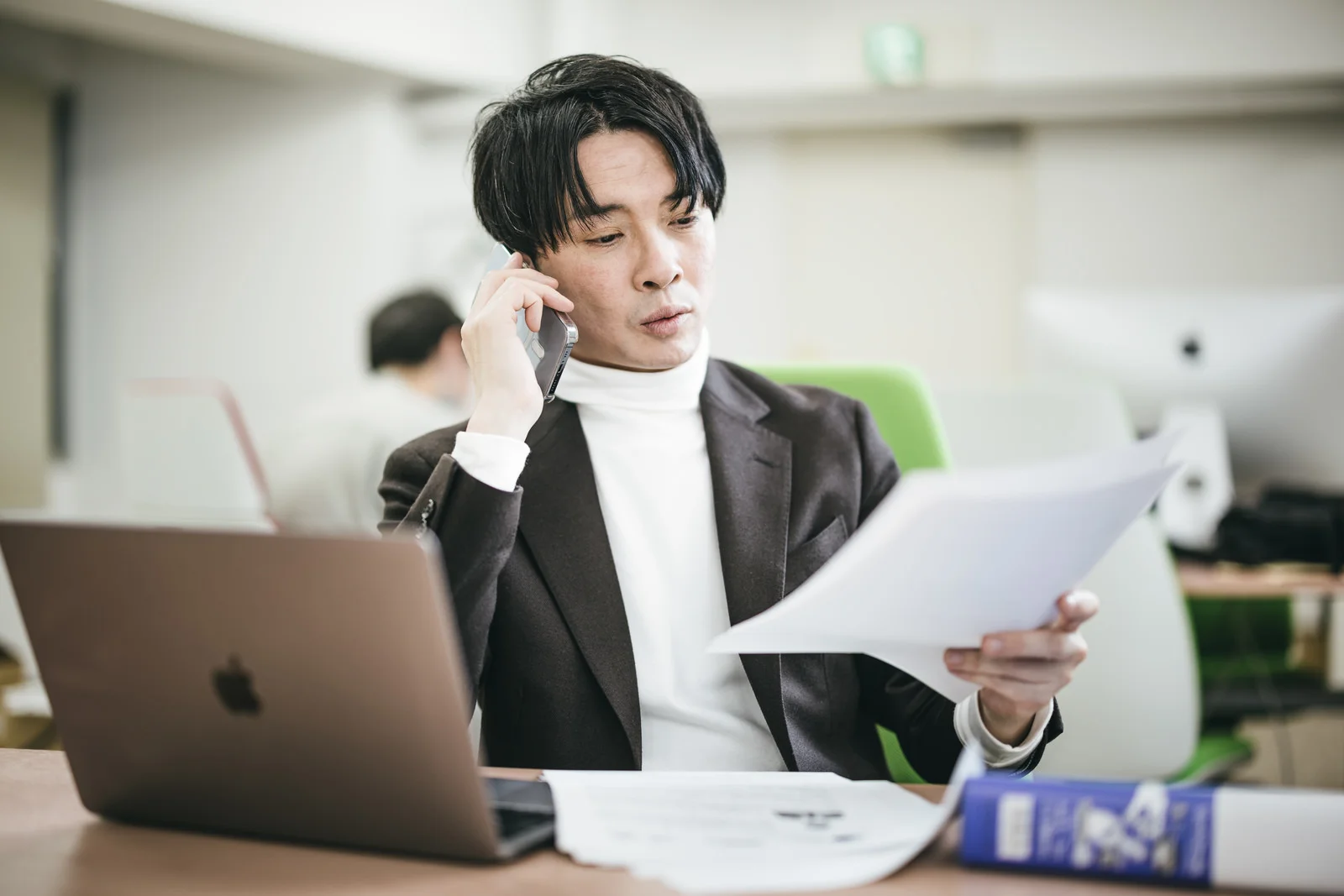ADHD傾向を持つ人々では、不安を感じやすいと言われることがあります。これは、ADHD傾向と環境からの影響が重なることで、不安が生じやすくなる場合があるためです。
ただし、こうした不安は改善のための工夫やサポートによって緩和できる可能性があります。この記事では、ADHDと不安の関係、その原因、そして改善策について紹介します。
ADHDと不安の関係
ADHDで不安を感じやすい背景には、いくつかの要因が考えられます。ADHDの特性が日常生活に与える影響に加えて、社会的な期待や環境の変化が不安を引き起こすこともあります。
タスク管理の難しさと不安感
ADHDでは、複数のタスクを同時に処理することや、時間管理が難しいと感じる場合があります。例えば、「締め切りまでに仕事を終わらせられるだろうか」「忘れていたタスクがあるのでは」といった不安が日常的に生じることがあるかもしれません。
社会的な期待へのプレッシャー
ADHDでは、周囲からの期待や評価に対してプレッシャーを感じやすいことがあります。「きちんとした印象を持たれたい」「もっと集中できる人だと思われたい」といった思いが、緊張感や不安感を増幅させる場合もあります。
過去の失敗体験の影響
過去にタスクを終わらせることができなかったり、注意力の散漫が原因でミスをしてしまった経験がある場合、それが記憶に残り、「また同じ失敗をしてしまうのでは」と考えることで不安が強まることがあります。
ADHDにおける不安の改善策
不安を和らげるためには、自分の特性に合った工夫を取り入れることが大切です。以下のような方法が、不安を軽減する助けになるかもしれません。
タスク管理を視覚化する
ADHDでは、タスクが複雑であったり、全体像が把握しにくいと感じることが多いと言われます。そのため、タスクを視覚的に整理する方法が役立つ場合があります。例えば、カレンダーやタスクリストを活用し、日々の予定を明確にすることで、「何をすればよいのか」がはっきりし、不安を減らせるかもしれません。
大きなタスクは細かいステップに分け、1つずつ完了させることで達成感を得ながら進めることができるでしょう。
リラクゼーション法を取り入れる
不安が高まったとき、深呼吸やリラクゼーション法を試してみるのも良い方法です。呼吸を整えることで、自律神経が安定し、緊張感が和らぐ場合があります。
過去の失敗をリフレームする
過去の失敗体験が不安の原因になっている場合、その経験を見直すことで、不安を軽減できる可能性があります。「あのとき失敗したおかげで、次にどのように改善すればよいか学べた」といった視点で考えると、過去の経験が自分を支えるものに変わることがあります。
専門的なサポートを活用する
不安が日常生活に大きな影響を与えている場合は、専門的なサポートを受けることも検討してみてください。カウンセリングや認知行動療法(CBT)は、不安に対処するための効果的な方法として広く知られています。
例えば、認知行動療法では不安の原因となる考え方のクセや行動パターンを見つけ、それを柔軟なやり方に変える練習を行うことで、不安を和らげる効果が期待されます。
不安を感じたときにできる即効的な対処法
不安が高まったとき、短時間でできる対処法も役立つことがあります。
- 「今」に集中する: 目の前にあるものを観察し、五感を使って「今ここ」に意識を向けると、不安感が薄れる場合があります。
- 短い休憩を取る: 不安で頭がいっぱいになったときは、5分だけその場を離れ、散歩をしたりストレッチをしたりして気分をリセットするのも有効です。
まとめ
ADHD傾向を持つ人々が感じる不安は、特性や環境から生じる場合が多いですが、自分に合った工夫を取り入れることで軽減できる可能性があります。視覚化したタスク管理や環境の調整、リラクセーション法の活用など、小さなステップから取り組んでみてください。必要であれば、専門的なサポートを受けることも、不安を和らげる重要な一歩となるかもしれません。
あいち就労支援センターでは、ADHDを持つ方々が安心して生活できるよう、不安のマネジメントの向上をサポートしています。お困りのことがあれば、ご相談してみてくださいね。