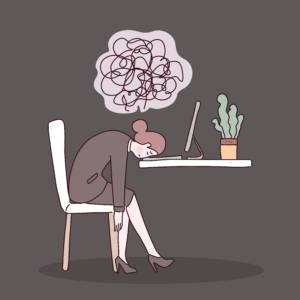「仕事に行こうとすると胸が苦しくなる」
「頑張りたいのに、どうしても心がついてこない」
「職場の雰囲気になじめなくて毎日が辛い」
そんなお悩みはありませんか?
環境の変化や強いストレスによって、心と体に不調が現れる状態を「適応障害」といいます。
職場や学校、家庭などでの人間関係やプレッシャーが原因になることが多く、誰にでも起こり得る心の反応です。
この記事では、適応障害の具体的な症状や治療法、セルフケアの方法をわかりやすく解説します。「もしかして自分も?」と不安な方や、周りに心配な人がいる方にとって、役立つ情報をまとめています。
適応障害とは
適応障害とは自分が置かれている環境に適応できず、ストレス反応として心身の症状が出現し、社会生活に支障が生じる状態です。
以下のような症状が2週間以上続く場合、注意が必要です。
精神的な症状
- 気分の落ち込み(抑うつ気分)や涙もろさ
- イライラしやすくなる
- 不安感や緊張感が続く
- 原因のわからない焦りを感じる
- 集中力の低下
身体的な症状
- 寝付けない・早朝に目が覚める
- 食欲の低下や増加
- 胃の痛み・動悸・頭痛
- 慢性的なだるさ
行動面の変化
- 遅刻・欠勤が増える
- 人との接触を避ける
- 物事にやる気が出ない
こうした症状や変化を見逃さず、自覚できるようになることが予防の第一歩です。
自分でできる簡易チェックリスト
ここでは、自分の状態を振り返るための簡単なチェックリストをご紹介します。
- 最近、会社(学校)に行くのがつらいと感じる
- 気分が沈んだ状態が続いている
- 寝ても疲れが取れない
- 以前楽しめていたことに興味がわかない
- 人と会うのが億劫になった
3つ以上「はい」がある場合は、専門機関への相談をおすすめします。
適応障害のメカニズム

適応障害の原因は「ストレス」です。
ただし、同じ環境でも発症する人としない人がいます。これは、ストレスの感じ方や受け止め方には個人差があるためです。
人間関係、環境の変化、業務の変化などを要因として、ストレスが「コップの水」のように溜まっていき、あるラインを超えるとあふれてしまう。これが適応障害のイメージです。
また、適応障害には以下のような特徴があります。
- ストレス要因が明確
- 症状が短期間で現れる
- ストレス因がなくなると軽減する
それぞれの特徴を一つずつ見ていきましょう。
ストレス要因が明確
適応障害の特徴の一つは、ストレス要因が比較的はっきりしていることです。
主なストレス要因としては、就学、就職、転職、部署異動、転居、結婚、対人関係の悩みなど、環境の変化に伴うものがあります。
これらの変化に適応できず、心身に不調をきたすことで適応障害の症状が現れます。
症状が短期間で現れる
適応障害のもう一つの特徴は、症状が比較的早い段階で現れることです。
環境の変化が起こった後、数週間から数ヶ月以内に体調や気分に不調が現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。
したがって、早期の対処が症状の悪化を防ぐために重要です。
ストレス因がなくなると軽減する
また、ストレスの原因が解消されれば症状が軽減していく一時的な反応であることも特徴の一つです。
例えば、転職や部署異動が原因で症状が現れた場合、その環境から離れることで症状が改善しやすいとされています。
ただし、問題の本質は環境の変化に対する適応の難しさにあるため、単に環境を変えるだけでは根本的な解決にはならないこともあります。
適応障害の治し方
適応障害と診断されたらどうすれば良いでしょうか? ここでは自身で行えるセルフケアの方法と、精神科や心療内科、カウンセリングルームといった医療機関、支援機関を利用した方法をご紹介します。
セルフケアによる治療法
休養を取る
適応障害と診断されたら、まずはしっかりとした休養が大切です。
就学や就職、部署異動といった、ストレス要因が学校や職場にある場合には一度休学、休職を検討しましょう。
上述の通り、適応障害では要因となった環境から離れて休養をとると、症状が軽減する傾向にあります。
ストレスの元を書き出してみる
自分が「何にストレスを感じているのか」を文字にして整理することで、気持ちの整理がつきやすくなります。
たとえば、「毎朝、職場を思うと気が重い」「上司とのやり取りがつらい」など、具体的に書いていくと、自分が何に反応しているのかが見えやすくなります。
小さなことでも可視化することで、必要以上に抱え込まず、現実的な対処がしやすくなります。
リラクセーション法
心と体をリラックスさせる時間を意識的に作ることも、ストレス軽減につながります。
深呼吸や軽いストレッチ、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、シンプルな方法でOKです。
好きな音楽やアロマなども取り入れて、自分なりのリラックス法を見つけてみましょう。
医療機関・支援機関による治療法
薬物療法
症状が強く、日常生活に支障がある場合は、医師が抗不安薬や抗うつ薬を処方することもあります。
不安感や不眠をやわらげ、心の安定をサポートする役割があります。
薬の使用には個人差があるため、医師と相談しながら無理のない方法を選びましょう。
カウンセリングで相談する
専門のカウンセラーに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが軽くなることがあります。
自分の気持ちを言葉にすることで、「なにがつらかったのか」「どうすれば楽になれるのか」が見えてくることもあります。
誰かに話すことは、回復への第一歩としてとても大切です。
認知行動療法(CBT)
適応障害の治療では、「認知行動療法(CBT)」というカウンセリング手法が効果的とされています。
自分の考え方のクセや、物事の受け取り方のパターンに気づき、より柔軟でストレスに強い考え方を身につけていく方法です。
たとえば、「失敗した=自分はダメだ」と感じてしまう場合、「失敗しても学べばいい」といった捉え方に変えていくようなイメージです。
認知行動療法では、自分の考え方のクセに気づきながら、ストレスマネジメントの力も少しずつ身につけていきます。
一人で変えるのは難しいこともあるため、専門家と一緒に進めることで、より効果的に取り組めます。
あいち就労支援センターでの対策

適応障害を治していくにあたって、当センターでは認知行動療法を中心とした支援を行っています。カウンセリングを行いながら、要因や背景に合わせて、その方に合った対処方法をともに検討し、試していきます。
生活リズムの安定化
中でもまず重要なのは「生活リズムの安定」です。
睡眠、食事、適度な活動と休養を安定して実施できるようにしていきます。
とくに、ストレスがかかると眠れなくなる、夜更かししがちになる、活動量が低下するなどの人は普段からリズムを保つようにします。
ストレス解消のアドバイス
また、ストレス解消方法の種類を増やすことも大切です。
体に負担のかかるようなストレス解消をしすぎていないかも確認します。
ドカ食い、お酒の飲みすぎ、ゲームのしすぎなどがこれにあたります。
考え方の幅を広げるサポート
考え方について「自分を責めてしまう」「周りの人と比べて不安になってしまう」などの考え方の癖があって苦しくなってしまう方もいます。
この場合、考え方の幅を広げて、よりバランスの取れたとらえ方ができるよう、カウンセラーと一緒に考えたり練習していきます。
スキルの再確認
以前の職場環境でスキルの不一致がみられることもあります。
この場合、改めてスキルを見直し、その方に適した環境を見つけることも大切です。
まとめ
適応障害は、環境の変化やストレスに適応できず、心身に不調をきたす病気です。
適応障害を放置すると、症状が悪化し、うつ病へ進行する可能性もあるため、早めの対処が重要です。
休養をとる、カウンセリングを活用する、ストレスとの付き合い方を学ぶなど、自分に合った対策を見つけましょう。
あいち就労支援センターでは、カウンセリングを通じて、一人ひとりに適した対処法を一緒に考え、生活リズムの安定やストレス解消法の見直し、考え方の幅を広げるサポートなどを行っています。
「少しでも当てはまるかも」と感じたら、ひとりで抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。
あいち就労支援センターでは、あなたの状況に合わせた無理のないサポートを大切にしています。